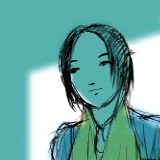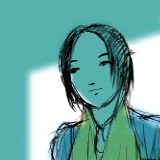|
画を放棄したというのにしつこくしつこく画の話。いや、むしろやめたからこそか。
画と音楽を比べると、画のほうがどこかいかがわしい雰囲気があるような気がするのは、私の偏見でしょうか?
例えば音楽を演奏する行為と、画を描くという行為、それぞれが目の前で展開していたとすれば、パフォーマンスとしては圧倒的に音楽のほうが有利でしょう。
前にも書いたことがありますが、音楽は言葉を介さなくてもその場にいる人が共有できるのですが、画の場合はそういうわけにはいきません。基本的にその画を見てどう感じるかはその人次第。隣で同じ画を見ても、必ずしも同じ感想を持つわけではありません。画を見るという行為は、実は孤独であることを強要されているのではないか、というのはちょっと考えすぎですか。
加えて、画というのはありもしないものをいかにもありそうに見せてしまうという側面もあります。シュールレアリスムを持ち出すまでもなく、私にとって馴染みの深いキャラ画はもちろん、この世界の一瞬を切り取る写生という手法にしたって、切り取ったその瞬間はもうそこには残っていないのですから、やっぱりありもしないものを描いていると言えるでしょう。
画というのはとどのつまり、ありもしないものをありそうに見せる、一種の詐術だといっても過言ではないかもしれません。
詐術といえば物語…いわゆるフィクションも、やはりありもしないことをさもあったかのように語るものであり、これもやはり詐術の一種です。画と物語にはだから元々親和性があるわけですね。ま、それはどうでもいいのですが。
重要なのは、いずれにせよ詐術を為すのだからそれなりの覚悟が必要であるということです。
画の技術というのは、基本的には「いかにもそれらしく見せる」ためのものだと言えるでしょう。つまり技術を追い求めるということは、見る者をより巧みに騙すことができるようになるということと同義なのです。画を描くからにはこのことにある程度自覚的である必要はあるでしょう。
ところが面白いことに、高度な技術を駆使して描かれた画が必ずしもいい画だとは限りません。皆さんにも経験があるのではないでしょうか? 形がきちんと整っていて構図も十分に練られている、にもかかわらずなんとなく面白くない。逆に、歪んでいたり粗かったりするのに妙に面白い。
これは一体何を示しているのでしょうか。
つまり、画を見る側は必ずしもうまく騙してくれることを望んでいるのではなくて、なにか心に引っかかることを期待して画を見ているということなのです。
技術ばかり追求するとつい忘れてしまいがちですが、画はどこまで行っても画でしかないのですから、いくらホンモノそっくりに見えても結局はニセモノでしかないのです。もちろん、やみくもにリアルに描くことそのものに何か明確な目的があるのなら話は別ですが、そうでないのなら自分がもっとも描きたいものは一体何なのかをはっきりと持っておくことが必要です。それが多分見た人の心に何か引っかかりを作るのだと思います。
んで。
反撃の狼煙、とまでは行きませんがとりあえず久しぶりに描いてみました。
肩の力を抜いていくといいのかもね。
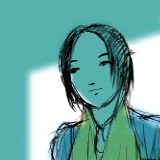
|