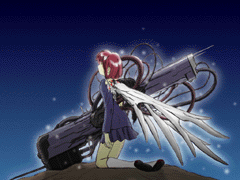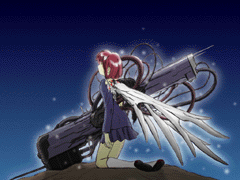|
この画は単行本第2巻p.22のコマを模写したものである。
このコマはちせの「兵器としての姿」を印象的に見せたコマだろうと思う。
背中から「生えた」翼は天使のような優美さと同時に、機械としての冷たさやグロテスクさをも併せ持つ。機関砲などによって肥大化した右腕のバランスの悪さは、そのままちせ自身の不安定さを表していると云ってもいいかもしれない。
勿論、こういった「戦闘少女」というモティーフは既に先行するマンガやアニメで見慣れたものとなっている。(某紙では「オタク的既視感」という言葉を使っていたが、なかなか巧みな表現だと云えるだろう。)
ただ、これほど痛々しい身体の表現は近年のマンガ・アニメ作品の中では「エヴァンゲリオン」ぐらいしか思い浮かばない。
つまりちせの身体とは、”何か”に蝕まれた不健康な身体性の表象なのである。
夥しい量の機器類と生身の肉体とが融合する、というイメージは「生物都市」や「AKIRA」などで示された、(そう云ってよければ)既に陳腐となったイメージと云えるだろう。そして現実に、今人間の肉体は既に様々な電子機器と融合を始めていると云ってよいところまで来ている。
例えば遺伝子組み替え技術や、人工臓器の研究。
或いは情報化技術による認知可能範囲の拡大。
これらは私たちのサイバーパンク的な想像力を励起すると同時に、得体の知れない不安までもかきたてる。この果てにあるのは、きっと、夥しい数の機器に繋がれた身体だろう。
(ちせのデザインがそうであるように、)この融合のイメージは常に正負の両義性を抱えている。
即ち、無数の機器類を従える万能の天使と、見る者を畏怖させる凶暴な悪魔。
人は機器を”身にまとう”ことによって飛躍的にその活動の可能性を広げることが出来るが、一方でそれは他者を(或いは自己をも)破壊する、決定的な”力”にもなりうる。
果たして、それだけ大量の”力”を私たちは適正にコントロールすることが出来るだろうか?
作中でのちせは、次第に「兵器の部分」に”蝕まれて”いく。
彼女は人間としての肉体を蝕まれつつも、それでも人間として(もっと云えば「女の子」として)生きようとする。
これを「物語だから」と一笑に付すことは容易である。
しかし、では(意識的にせよ無意識にせよ)現実に「機器に蝕まれつつある」私たちはどうだろうか?ちゃんと人間として生きようとしているだろうか?
私たちは無数の電子機器に取り囲まれて便利な生活を謳歌しつつも、結局は心を満たすことが出来ずにいる。直接痛みを感ずることも無く、自分の見えないところで人を傷つけている、そんな暮らし方をしている。
一方、ちせは自らの身体を傷めて、自分の手で命を奪っている。
だから、ちせの痛みは巡り巡って私たちの痛みでもある。
この痛みを引き受けられなければ、私たちに未来は無いように思う。
痛みをその身に引き受けることの出来ない者に、恋が出来ないように。
参考文献:
夏目房之介「マンガと『戦争』」(講談社現代新書刊)
大澤真幸「虚構の時代の果て―オウムと世界最終戦争」(ちくま新書刊)
|