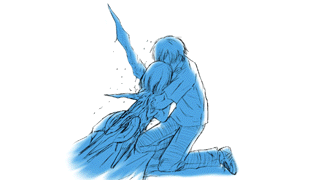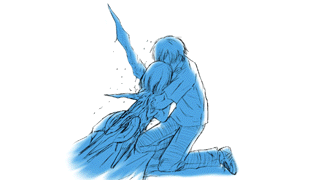
知らなければこんなにつらい気持ちになることなんてなかった。
目をふさいで誰とも知り合わずに生きていたら。
ただ一人だけで生きていたとしたら。
「最終兵器彼女」第7巻より
|
|
はじめに
この文章には敢えて些か刺激的なタイトルをつけましたが、私自身の立場としては「最終兵器彼女」というマンガを今でも擁護しています。
この物語に対しては賛否両極端の評価があり、どちらも感情的になってしまいがちです。まあ、作者は読者が冷静に読めないような仕掛けをたくさん用意しているので、当然と言えば当然です。両者ともまんまと作者の術中にはまっていると言ってしまえばそれまでなのですが、私としてはどちらにも簡単に同調できず、困っている次第です。
そこで、いっそのこと作者の仕掛けはこの際放っておいて、ごくごく冷静な目でこの物語を眺めることは出来ないだろうか、という個人的な興味から企図したのがこの文章です。したがって、何が書いてあるのかいまいちわかりにくいだろうと思います(一応途中までは理解してもらう努力をしてみたのですが…)。
それでもよければ読んでみてください。
※以下はマンガ「最終兵器彼女」をテクストとしたもので、アニメ版は筆者未見のため対象とはしておりません。またネタばれとなるので未読の方はお読みにならないほうがよいかと思います。
|
|
1.可塑的な身体
あなたは自分の身体を改造したい、と思ったことはないだろうか?
何もサイボーグのようなグロテスクな話ではない。
例えば男性がマッチョなボディーを目指してジムに通ったり、女性が美しい身体を獲得するためにエステに通ったり。そんなレベルの話。拡大解釈すれば、落ちた視力を補うために眼鏡をかけたりコンタクトレンズを入れたりすることも「改造」と云えるかもしれない。そういうレベルまで含めたら、自分の身体を改造したい、改造しているという人はかなりの数にのぼるはずだ。
身体の改造、という発想自体は別に目新しくも何ともない。ヨーロッパ女性のコルセットや中国の纏足などはその典型だし、眼鏡の例を援用すれば戦争の際に剣を帯び鎧をまとうのだってその範疇に含まれるだろう。
そもそも、自分の肉体を変えたい、という欲求は基本的な欲求の一つではないだろうか?「ひ弱な猿」が圧倒的な自然に対抗するための手段を求めたように、石器時代の昔から今に至るまで脈々と受け継がれてきた欲望なのではないか。
今、私たちが自分たちの身体に対して抱いているイメージとはどのようなものだろうか?なんとなく、自分の思い通りになるようなイメージを持ってはいないだろうか?
容姿などは美容整形で思い通り操作することが出来る。
必要な栄養素は栄養補助食品で補えるから好きなものしか食べない。
そこまで極端な考えの人は滅多にいないと思うが、今やろうと思えばまったくの不可能ではないから、あながち外れてもいない。
「こうしたい」と思えばそのように改変できてしまう、可塑的な身体。
しかし、そうして獲得された身体を、私たちはどれだけ実感できているだろう?
どれだけ強くなったか。どれだけ美しくなったか。
「最終兵器彼女」の中で、ちせの身体は非現実的な可塑性を示す。右腕は機関砲に変わり、背からは金属の翼が皮膚を突き破るようにして「生え」、彼女の身体にはグロテスクなまでに「人間以外」の部分が付加されていく。のみならず、最終巻では分子・原子レベルでのコントロールが可能であるようにさえほのめかされる。原理はどうあれ、身体の改造としては究極的な発想だと云えるだろう。
冒頭挙げた喩えとはずいぶんとかけ離れているように見えるが、しかしどちらも貫いているものは同じだと私は思う。
「今よりももっとこうなりたい」という、単純な願望だ。
ちせの身体は「強くなりたい」という彼女の素朴な言葉を、直喩的な表現として見せてくれる。彼女は無制限に「強さ」を望み、彼女の身体はそれに応えるように無制限な「破壊力」を備えていく*1。それでも彼女は「強くなった」という実感が持てず、更なる「強さ」を求めてしまう。どこまでも際限なく。
この身体に対する「実感のなさ」は、実は私たちが持っているものと同じものではないだろうか。例えば普段何気なく口にする「なんとなくだるい」という言葉は、身体の不調を表わしはするものの具体的にどこがどう不調なのかを全く示さない。きっと私たちは自分が思っているほどには自分の身体のことをわかっていないはずだ。
恋愛においては「性」という局面で身体が重要な役割を果たすが、この物語では性行為によっても身体に対する実感が回復されることはない。
では、この「実感なき身体」の上に成立する恋の形態とは、一体どのようなものだろう。
|
|
2.「純愛」という観念
シュウジとちせの物語で特徴的なのは、薄れてしまった身体性を回復するのではなく、敢えてそれを失ったものとして受け入れて(喪失した身体はそもそも不可逆なものとして描かれている)、その上でなお恋を続けているところだ。過剰な可塑性によってちせの身体が既に人間でなくても、かすかに残るその痕跡を根拠に恋を続ける。二人は性行為によって一時的に肉体的な一体感を得るが、最終的にはそれすらも失ってしまう。果たしてそれでも恋を継続することはできるのだろうか。
考えられる可能性は一つだ。
身体を超えた精神的な一体感のみによる恋愛。
それはまさに「純愛」と呼ばれるものであり、(実在するのかどうかは知らないけれど)多くの人が憧れを抱くものでもある。
他方これが、この物語が批判に晒される一つの原因でもある。
例えば社会性の欠如とか、胎内回帰だとか。
まあ、一部の心無い中傷は措くにしても、この物語のラストに違和感を覚えた人は少なくないだろうし、それはあながち間違いではない。
常識的に言えば、恋の終わりは(そのバリエーションは数あるが)感情の冷却による別れか、愛情への昇華による発展的な解消かのどちらかしかありえない。したがって、そのどちらでもないこのラストは現実の恋愛の諸相からすると極めて特異なものであると言えよう。社会的に祝福されるのは勿論後者であり、一般には「結婚」という形で制度化されたものに繋がる。
恋愛も結婚も縁遠い私が論じるのもおこがましいが、敢えてその違いを一言で言えば、「恋愛」は当人同士の関係性の問題に過ぎないが、「結婚」はその親族を巻き込んだ社会的な関係性の問題だと言うことが出来る。或いは、恋愛は当事者の感情のドラマだが、結婚は社会的な儀礼のドラマだと言い換えてもいいだろう。
家庭とは基本的には新たな血縁者の再生産の場であり(無論そうではない場合もあるのだが)、いくら日本国憲法が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立(第24条)」すると明記していても、現実的には結婚する際には当事者だけでなく互いの両親をはじめとする親族とも新たな関係(「回避」という否定的な関係をも含め)を築き上げなければならない。
したがって、新婚家庭は決して「二人だけの世界」ではない。
一方、「純愛」とは身体性を超えた恋愛であると想定すると、これは精神的な一体感を疎外する一切の要素を二人の間から排除しようとする。自分の考えたことは相手も同じように考えるし、相手の考えたことは即ち自分の考えたことであり、すべて二人の内部で完結する「二人だけの世界」という観念こそが、「純愛」の正体である。したがってその外部である社会関係は、当然「純愛」の阻害要因として排除の対象となるだろう。制度としての結婚が二人の恋愛関係を社会という仕組みの中に組み込むものである以上、「純愛」を目指す二人のゴールは結婚ではありえない。
二人で手に手を取って遠くの土地へ逃げ出す「駆け落ち」や、互いに自死を選ぶ「心中」などは、こうした観念を突き詰めた果ての行為だと理解されるが、当然このような行為は反社会的な行動だから、社会から弾圧を受けもする。
ただし、「駆け落ち」が既存の社会からの遁走、「心中」が互いの身体を滅ぼすことによる社会の殺害*2であるのに対し、シュウジとちせの物語は文字通り社会を滅ぼすことによってこの観念の実現に至る点が従来の物語になかったと言えるだろう。
シュウジとちせの物語は「恋愛→結婚」という社会的なドラマへは繋がらず、といって従来の心中もののような自滅の物語でもなく、「純愛」という美しくも恐ろしい一種の原理主義的*3な結末を導いた。
では、それは一体何故なのだろう。
|
|
3.「信じる」こと
この物語には通奏低音として「戦争」が常に流れている。
「最終兵器彼女」での戦争の描かれ方の特色として、政治的・軍事的な事情などを一切排除した「状況」として描かれていることが挙げられる。
「敵」が一体どこなのか、何が原因で戦争になったのか、そういったことには一切触れず、ただ目の前で展開される戦闘だけを執拗に描写するという描き方は、単に読者の感情移入を容易にするという、作劇技術上の理由だけではないだろう。
この物語における「戦争」は、敢えてそうした背景の描写を排除することによって一切を破壊する行為の象徴としての役割を果たしている。
現実の戦争はいかなる場合も利害なしに勃発することはないし、そこで戦われる正義についてはいやというほど喧伝される。しかし、私たちは(平和な国に住む第三者として戦争を眺めるならば)そうして喧伝される戦争の原因というものが必ずしも真実でないことを知っているし、戦争の渦中にあってはその原因や正義といった抽象論はさして重要でなく、むしろ自らの生命の処遇のほうが重要になるだろうということを想像することは出来る。原因や正義は戦争を進行させる意志にとって重要であっても、身体にとっては「言い訳」程度の重要性しか持ち得ない*4。人は「何故か」を知らなくても行動することが出来てしまうし、一旦それらしい理由が与えられて疑うことを止めてしまいさえすれば、あとはどこまでも際限なく信じることが出来てしまう。目の前で進行していることを、一切の疑問や判断を交えずにただ「信じる」ことが、戦闘という行為を支え、戦争を進行させる。
この「信じる(=疑わない)」*5という一線を踏み越えた時に、人は冷酷な虐殺者になることができるのだ。
そしてシュウジとちせの物語もまた、「信じる」ことの物語だ。
何故相手のことが好きなのか、何故相手のことを想っているのか、最初はその理由を思い悩んだり、また相手に対して信じきることの出来ない部分があるからこそ嘘を求めたりする描写が展開される。
しかし物語の終盤では、混乱の中でちせがシュウジだけを隔離することができたように、或いは変わり果てたちせの姿を見てもシュウジがちせだと認識できたように、二人はただ「信じる」ことが出来るようになる。際限なく相手を「信じる」ことが出来た時、二人の恋愛は「純愛」の地平にまで推し進められたと言えるだろう。
その時、既に世界が破滅を迎えていたことはある意味必然である。
ちせの身体は、前述したように極端な可塑性を備えていく。彼女の身体は一切の破壊的行為の象徴である「戦争」のメタファー*6として機能し、「戦争」の進行にしたがってその破壊力も加速度的に増大していく。
一方でまた、彼女の身体はどこまでいってもただの女の子でしかないから、ただの男の子であるシュウジに恋をする。
両者の落差が激しければ激しいほど、ただ「信じる」ということでしか二人は繋がることが出来なくなる。ちせの身体がどれだけ人間からかけ離れようとも、シュウジがそれをちせだと信じる限り、ちせは彼女自身でありつづけられる。だから、シュウジはちせだけを信じつづけなければならないし、ちせもまた彼女自身を維持するためにシュウジを信じなければならない。他の一切の観念は必要ない。多分に自己欺瞞的な要素*7を孕みつつ、前述した「二人だけの世界」という観念が発生するわけだ。
一切の疑問も判断も必要ない世界。それは文字通りただ二人だけが存在し、他の一切のもの(二人を煩わすものは勿論、二人を助けるものも含め)が存在しない世界なのだ。
そして、ちせにはこの「二人だけの世界」を実現できる身体が備わってしまっている。
すべてを破壊する力を備えた、「戦争」のメタファーとしての身体。
この身体によって、シュウジとちせは「二人だけの世界」―すなわち二人以外のすべてが絶滅した、美しくも荒涼とした世界を実現したのだ。
|
|
4.「絵空事」のリアリティー
実感の欠落した身体が過剰な精神的な繋がりを励起し、遂には世界を滅ぼす。
この作品のラストに怒る人がいるのはもっともなことだろう。
一方で、このラストを絶賛する人もいる。
実際の恋愛では「純愛」をこのような形で実現することは(すべてを破壊し尽くす身体が獲得できない以上)どうあがいても不可能なのだから、このラストをどう評価するかは完全に読者の自由だと言える。絶滅した人類に自分を重ねれば、自分のすべての価値を否定された気分になるだろうし、シュウジやちせに自分を重ねれば、実現不可能な「純愛」を実現したことを羨ましく思えるだろう。
経験の乏しい私が言っても何の説得力も無いが、実際の恋愛では身体を介在しなければならない局面の連続だろうし、何も結婚にまで至らなくても社会関係(例えば友人関係など)から完全に自由なわけではない。特定の局面では「疑い」もまた重要な要素だろう。別個の身体を有する二人が身体を超えて精神的に繋がる、という「純愛」の観念は、身体的にも観念的にも成立する可能性はきわめて低い。
したがって、「純愛」など現実の社会にははじめから存在しない、と言い切ってしまっても過言ではないだろう。「最終兵器彼女」の物語は、文字通り「絵空事」でしかない。
しかし、いまさらそんな前提を提示したところで何の意味があるだろう。この物語を読んだ人々は、これがフィクションであることを十分に認識しているはずなのだから。
ただ、恋愛の根拠となるべき「身体に対する実感」が薄れつつあるのもまた事実だ。
「純愛」がたとえ絵空事であっても、その物語に価値が無いわけではない。フィクションだからこそ現実に存在しないものを描くことを許され、またそこに描かれたものから現実を考えることも許されるのである。物語の価値は、物語そのものにあるわけでなく、それを読んだ読者が与えるものだ。だから、この物語のリアリティーは、読んだ私たちの中にこそ存在する。
果たして、あなたの感じたリアリティーは、どのようなものだったろうか。
|
|
おわりに
以上、なんだか偉そうに小難しいことをずらずらと並べてみましたが、結局個人的に考えてきたことをちょっと整理しただけで、内容的にはこれまで「最終兵器彼女をめぐって」に書いてきたことと大差ないように思います。
マンガのよいところは、このような実際にはありえないことでも、とりあえずありそうなことのように描くことが出来る点にあります。作者である高橋しんさんはこの辺りのことを十分熟知されているでしょうし、私たちもそのことについて十分理解しなければならないと思います。そのためには一歩引いた立場から眺めてみることも、時には必要だろうと思うのです。
この文章によってそういった視座を提供できたとしたなら幸いです。
ご意見やご感想、質問などがありましたらこちらからどうぞ。反論も可です。
|
注:
1.ちせの「強くなりたい」という口癖中の「強さ」とは精神的な強さのことであって、身体的な強さを意味しない、と解釈することも出来る。しかし、本編を精読しても両者が峻別された描写はない。彼女が「強さ」を求める動機は「シュウジを守りたい」と記述されているだけである。これは作者の錯誤ではなく、意図的に両者を混濁させた表現を目指したと受け取るべきである。
2.食事をはじめとして、身体の維持には多くのエネルギーを必要とする。そのエネルギーを複数の者で分担することによって個々人の負担を軽くすることを社会の目的と考えるならば、社会と身体とは共依存の関係だと言えるだろう。自らの身体を殺害するという行為はこの「社会に依存した身体」を否定するものであり、したがってそれは社会そのものをも否定したことになる。
3.「原理主義的」という言葉について。ここではあらゆる現実のしがらみを無視して観念に従うことを是とする、という文脈で使用した。この言葉は「イスラム」という枕詞がついて使用されることが多いが、キリスト教にも原理主義者はいるし、原理主義がすべて過激な社会攻撃を志向するわけではない(以上蛇足)。
4.身体と精神の二元論的な考えに立てば、身体は精神の「いれもの」以上の意味を持たない。したがってこの立場に立てば、精神のない身体はどのように利用してもよいことになるし、精神さえ保存できれば身体は何でも構わない、という極論も生じうる。身体は精神の「可処分所得」と考えるわけだ。戦争において「意志の元に死ぬ」ことを選ぶことは、このような心身二元論的な考えから生じたと考えることが出来る。しかし、一方には身体と精神とは不可分だという考えもある。その考えに立てば、身体は精神の発生源であるから、精神がその意志で自らの身体を滅ぼすためには何らかの「言い訳」をつけなければならない。戦争における大義とは、いかに自分の死を正当化できるかが重要なのである。
5.「信じること」=「疑わないこと」と言い切ってしまうのは些か乱暴な議論だろう。あることを「信じる」ためには(客観的・主観的)根拠が必要であり、その根拠が薄弱な時に人はそれを「疑う」。では単純に根拠の多寡でこの両者が分かれるのか、というとどうもそうではないらしいのだが、これを追求するとトートロジー(同義反復)に陥るおそれがあるため、ここでは深く言及しないことにする。
6.ここでは「隠喩」と同義に使用した。
7.本稿では「信じる」という言葉を「疑わない」ことと同義に扱ったため、倫理的な疑問(世界を滅ぼすことの是非善悪…等)も封じられることになる。本編においてそうした問いが完全に封じられたわけではないが、決断の局面では倫理ではなく恋という観念を優先した決断がされ、しかもそれが最悪の結末を招くであろうことをシュウジもちせも十分に認識している。その上で、この物語では敢えて恋を選び取り、その結果を取り返しようのない重大なものとして描いた。その意味においてここでは「自己欺瞞的」と表現した。
参考文献:
笠井潔「テロルの現象学」(ちくま学芸文庫刊)
大澤真幸「虚構の時代の果て―オウムと世界最終戦争」(ちくま新書刊)
小谷野敦「もてない男―恋愛論を超えて」(ちくま新書刊)
夏目房之介「マンガと『戦争』」(講談社現代新書刊)
養老孟司「唯脳論」(青土社刊)
山口意友「正義を疑え!」(ちくま新書刊)
|